
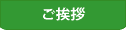 |
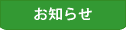 |
 |
 |
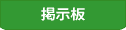 |
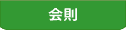 |
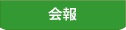 |
TOP > ご挨拶
 |
|
2005年12月吉日
久留米大学法学部卒業生各位
久留米大学法学部同窓会
会長 折戸謙介
会長就任の挨拶
謹啓 卒業生の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
私は、5月15日の同窓生集会において承認され、新しく発足した久留米大学法学部同窓会の会長に就任致しました第5回生の折戸です。
第5回生の私は今年で33歳になります。そこから逆算すると第1回生の先輩方でも、平均40歳前ということになります。そう考えると、久留米大学法学部はまだまだ本当に若い学部であることが分かります。要するに、私たち卒業生は諸先輩方が長年作り上げていった伝統を重んじ、遵守していく立場にいるというより、私たち自身が伝統を作り上げて行かなければならない立場にいると言えます。 卒業生で構成するいわゆる『同窓会』という組織は、卒業生の間に入り、その結束を強めて、久留米大学法学部の名前を世間に対して積極的に宣伝していかなければならない責務があると思います。そうした活動を長年に渡って続けていくことで、初めて大学、学部の伝統というものが形となり、世間に浸透していくのだと私は考えています。 残念ながらこれまでは、そうした役割を果たしてくれる『同窓会』という組織は久留米大学法学部にはありませんでした。こうして新しい組織が発足しなければならなかった経緯や、これまでの同窓会がどのような組織であったかといった説明はここでは省略させて頂きますが、その点は非常に遺憾に感じております。新しく発足したこの同窓会は、そういったこれまでの過ちを踏まえて運営していかなければなりません。 前述しましたとおり、久留米大学法学部はまだまだ本当に若い学部です。久留米大学の他の学部に比べても若いですし、他の大学に比べても若いでしょう。若くて伝統がないということは、年配の方々からは、それのみを理由として批判を受けがちです。しかし、それを逆手にとり、若さを前面に出して柔軟な発想で活動が出来ればよいな、と思っています。世間的なイメージでの同窓会の集会とは、出世した人や、会社を経営するようになった人が営業のために参加して名刺を交換する集会であるという側面が強いのではないでしょうか。そういった側面も当然に必要ですし、なくてはなりません。しかし、それだけでは参加者が限られてしまいますし、若い世代で構成する私たち法学部の同窓会にはそぐわない気もします。もっと全ての卒業生が参加したくなるものでなくてはなりません。 長引く就職難の中で、失業や転職するケースも現実にあると思います。失職し、自分の方向性が全くわからなくなってしまう時期があった方や、今現在まさにそうである方が卒業生の中にもたくさんおられるのではないでしょうか。私もそうした時期があり、非常に孤独であり、出口の見えないトンネルの中にいるようでした。同窓会は、そうした時の相談の場や、情報交換の場でもありたいと思いますし、そうであるべきです。若干ネガティブな視点かもしれませんが、そういった視点も持っていたいと思います。 私以外の他の同窓会役員の方や、卒業生の方と話をしていると、同窓会にやって欲しいという意見や案、アイデアを本当にたくさんお聞きしました。その内容のすばらしさや、豊富さには驚かされることが多々あります。そうしたご意見を出来るだけ無視することなく検討し、取り入れ、それらを具体的な形にしていきたいと思っています。 しかしながら、現実問題として、当面はこれまでの残務処理であったり、組織や会則の編成、名簿の再編といった作業に追われたりすることになりそうです。新たな同窓会の活動が、具体的に卒業生の皆様の目に届くようになるには多少時間がかかるでしょう。その点をあらかじめご了承ください。 また、当面の間(数年間は)は卒業生の皆様から同窓会費は徴収しないことを決定しておりますことを明記しておきます。入学時に徴収する同窓会の入会金収入のみで同窓会の運営は十分にできます。そうした決定をした理由の一つには、会費を払っていないから同窓会には参加出来ないのだと誤解されている卒業生の方が多数おられたからです。同窓会に参加する資格が卒業生のすべての皆様にあることは、今更言うまでもありません。 今回の新たな同窓会の発足には、大変な労力が必要でした。産みの苦しみが大きかっただけ、この同窓会はより良いものになると確信しております。 最後になりますが、卒業生の皆様には、ますますのご発展とご活躍を心からお祈りいたします。 謹白
|